心臓の役割
心臓は人間が生きていく上でとても大切な臓器です。
人間は、呼吸をすることによって肺で酸素(O2)を取り込み、二酸化炭素(CO2)を吐き出しており、その酸素や二酸化炭素は血液を介して全身を循環しています。また、栄養素やホルモン、免疫細胞なども血液を介して全身を循環しています。
心臓は、その大事な血液を肺や全身の組織に送り出すポンプの役割を担っています。
心臓には、2つの強力なポンプと2つの弱いポンプの計4つのポンプが内蔵されています。
2つの強力なポンプのことを、それぞれ右心室と左心室といい、2つの弱いポンプのことを、それぞれ右心房と左心房といいます。中でも左心室が最強のポンプとなっています。
これらの役割は、血液の流れをみてみるとよく分かります。
- 肺でO2をたっぷり受け取り、CO2を吐き出しきった血液は、肺静脈を通って左心房、左心室の順に移動
- 左心室がもつ最強のポンプ機能により動脈を通って全身の組織に行きわたる
- 全身の組織を通過する際、血液はO2を組織に渡し、CO2を受け取る
- 全身の組織から静脈を通って右心房へ移動
- 右心房、右心室の順に移動した後、肺動脈を通って肺へ帰る
まとめますと、
肺→肺静脈→左心房→左心室→動脈→全身→静脈→右心房→右心室→肺動脈→肺
といった流れになります。
この流れが絶え間なく維持されていることが、我々人間が生きるためには不可欠なのです。
心臓の構造
人間が生きるために必要な臓器「心臓」。
一体、どのような構造になっているのでしょうか。
心臓は、主に以下の4つの要素によって成り立っています。
- 作業心筋
- 電気伝導系
- 冠循環
- 弁
作業心筋
「作業心筋」とは、心臓から血液を送り出すためのムキムキの筋肉のことです。
このムキムキの筋肉がギュッと収縮することで勢いよく血液が心臓から全身へ送り出されます。
筋肉のムキムキ具合は、場所によって異なっており、
左心室>>右心室>左心房≒右心房
といった順にムキムキになっています。
左心室と右心室の間には仕切りがあり、心室中隔と言います。
また、左心房と右心房の間にも仕切りがあり、心房中隔と言います。
さらに、少しマニアックではありますが、心房と心室の境目は左右で高さが異なるため、右心房と左心室の間にも仕切りが存在します。このことを房室中隔と言います。
電気伝導系
作業心筋が、各々、好き勝手なタイミングで収縮してしまうと血液を効率的に拍出することはできません。ですので、これらをコントロールするためのシステムが必要となります。それが、「電気伝導系」です。
電気伝導系は、リズムを生み出し、そのリズムを作業心筋に伝えることで、我々の心臓は絶え間なく、動き続けることができるのです。
電気伝導系は、場所によって名前が異なり、
洞結節→右心房、左心房→房室結節→His束→右脚・左脚→Purkinje線維→右心室、左心室
の順に電気が伝わっていきます。
冠循環
作業心筋や電気伝導系は、人間が生きている間、常に動き続けています。そのため、かなりのエネルギーを必要とします。そのエネルギーを各心筋細胞に届けるためのシステムのことを「冠循環」といいます。
冠循環のうち、エネルギー供給のための、上水道のような血管を冠動脈といい、老廃物排出のための下水道のような血管を冠静脈といいます。
弁
血液が一方向に絶え間なく流れることが循環にとって大切であることは前述させていただいた通りです。
血液が一方向に流れるようにするためには、ポンプ-ポンプ間やポンプ-大血管(大動脈や肺動脈)間での逆流を防止するシステムが必要となります。それが“弁”です。
心臓には4つの弁があり、以下のように場所によってそれぞれ名前が異なっています。
- 大動脈弁 :左心室と大動脈の間
- 僧帽弁 :左心房と左心室の間
- 肺動脈弁 :右心室と肺動脈の間
- 三尖弁 :右心房と右心室の間
まとめ
今回は、心臓の大まかな基本構造について説明させていただきました。これらの構造はどれも大変重要な役割を果たしており、一つでも構造に欠陥があると、途端に心臓の機能は低下し、「疾患」が生じます。欠陥がひどいと、日常生活に支障をきたし、最悪の場合、死に至ります。この欠陥を修復し、欠陥による機能低下を補うようなシステムを構築することで、患者さんの日常生活や命を守ることが我々、心臓血管外科医の使命だと思っています。
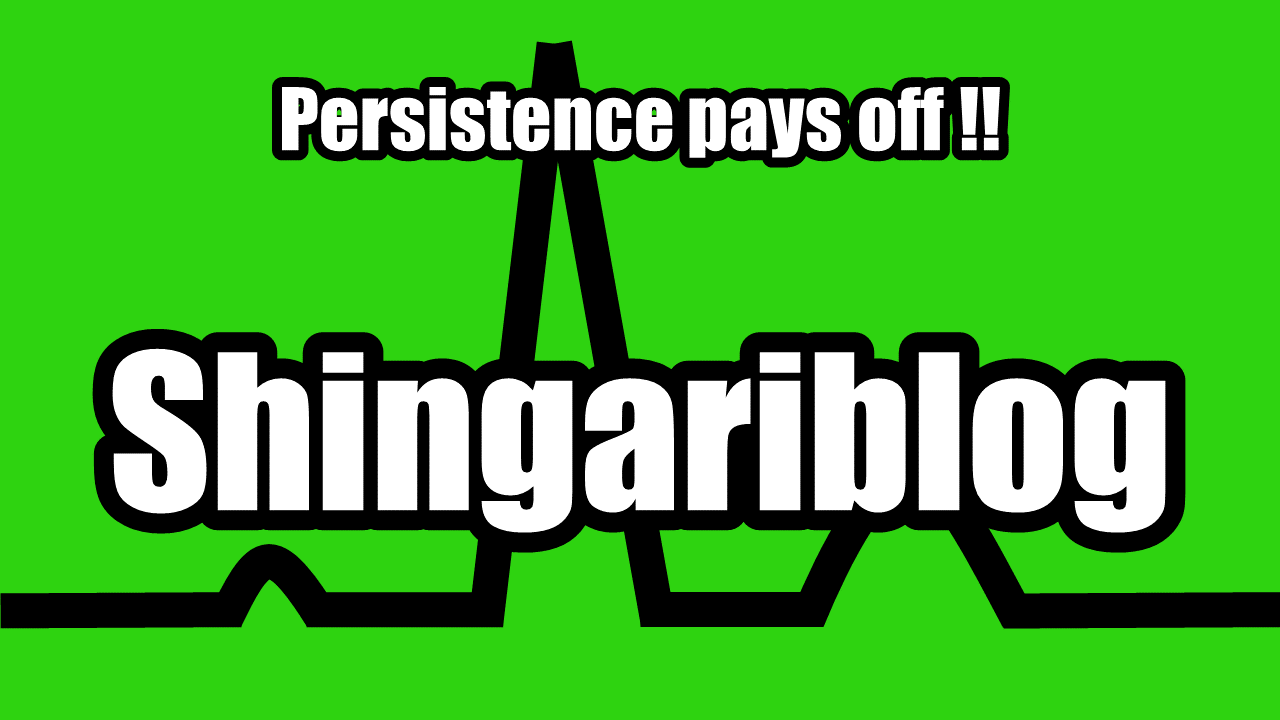



コメント