今回は、鈍的心損傷(Blunt Cardiac injury; BCI)についてまとめてみました。
あまり頻回に出会うものではありませんが、以前に方針に関して少し悩んだことがあり、より自信をもってアセスメントできるように勉強してみました。
救急医療に携わる医師、研修医、看護師向けの内容になっています。
疫学と分類
鈍的心損傷がどれくらいの頻度で発症するのかは、はっきりと分かっていません。
「Cardiac contusion (心挫傷)」や「Myocardial contusion (心筋挫傷)」という用語が臨床でよく用いられていますが、それらの定義が曖昧であることや、鈍的心損傷自体の明確な診断基準もなく、信憑性の高い検査もないことが原因です。
ゆえに、近年、より具体的な表現が望ましいと言われるようになってきました。
まだあまり救急医療には普及していませんが、American Association for Surgery of Trauma (AAST)が提唱したHeart injury scaleという簡便なツールがあります。
| Grade | 損傷の程度 |
| Ⅰ | ・マイナーな心電図異常(非特異的なST-T変化、SVPC、VPC、洞性頻脈の遷延)を伴う鈍的心損傷 ・心損傷、心タンポナーデ、心臓ヘルニアを伴わない鈍的・穿通性心膜損傷 |
| Ⅱ | ・伝導ブロックまたは虚血性変化を伴う鈍的心損傷(心不全は伴わない) ・心タンポナーデを伴わない接線方向の穿通性心損傷(心内膜に及んでいるが貫通していないもの) |
| Ⅲ | ・持続性または多源性の心室性不整脈を伴う鈍的心損傷 ・中隔破裂、肺動脈弁・三尖弁機能不全、乳頭筋機能不全、遠位の冠動脈閉塞を伴う鈍的・穿通性心損傷(心不全を伴わない) ・心臓ヘルニアを伴う鈍的心膜損傷 ・心不全を伴う鈍的心損傷 ・心タンポナーデを伴う接線方向の穿通性心損傷(心内膜に及んでいるが貫通していないもの) |
| Ⅳ | ・中隔破裂、肺動脈弁・三尖弁機能不全、乳頭筋機能不全、遠位の冠動脈閉塞を伴う鈍的・穿通性心損傷(心不全を伴う) ・大動脈弁・僧帽弁機能不全を伴う鈍的・穿通性心損傷 ・右心室、右心房損傷を伴う鈍的・穿通性心損傷 |
| Ⅴ | ・近位の冠動脈閉塞を伴う鈍的・穿通性心損傷 ・左室穿孔を伴う鈍的・穿通性心損傷 ・<50%の組織欠損を伴う放射状の右心室、右心房損傷 |
| Ⅵ | ・鈍的心臓裂離 ・>50%の組織欠損を伴う穿通性心損傷 |
発症メカニズム
ほとんどは交通外傷で発症し、そのほとんどは減速外傷によって発症します。一方で、直接打撃による発症も多く報告されています。
発症機序としては、心臓が胸骨と椎骨に挟まれたり、胸部や腹部に急激な圧変化が起こったり、急な減速により剪断力が働いたり、骨折した骨片が心臓を傷つけたりすることで発症すると言われています。
また、特殊なものとしては、心臓振盪(ボールなどが胸部を強打し、突然心停止する)という病態もあります。
損傷部位
前胸部に最も近いためか、右心系が最も損傷を受けやすいと言われています。
心室損傷も心房損傷も同等に報告がありますが、剖検例では、心室損傷の方が多く認められています。
位置やコンプライアンスが影響しているのかもしれません。
その他、稀ではありますが、弁損傷、中隔損傷、冠動脈血栓、冠動脈裂傷などの報告もあります。
他臓器の外傷の合併
BCIは、他の外傷(頭部、胸部、腹部、椎骨)をよく合併します。
15000例のBCI患者を含んだUnited States National Trauma Data Bankによる8年間のreviewによると、BCIに最も強く関連した所見は心膜血腫(OR 9.58)であり、胸骨骨折や胸部大動脈損傷の所見を認めた場合よりも2倍の頻度でBCIを発症していました。
Grigorian A et al. Am J Surg. 2019;217(4):639
胸骨骨折との関連性はある?ない?
胸骨骨折とBCIの関連は多くの観察研究で報告されています。
高所転落により死亡した患者の剖検研究では、BCI患者の76%で胸骨骨折を認め、一方で、BCIを伴わない胸骨骨折患者はたったの18%でした。
Turk EE et al. J Trauma. 2004;57(2):301
また、German trauma databaseによるreviewでも、胸骨骨折におけるBCIのリスクはかなり高いと報告しています。
Hanschen M et al. PLoS One. 2015;10(7):e0131362
しかし、複数の研究で、CTでのみ指摘できるような胸骨骨折はBCIを必ずしも示唆しているわけではなく、胸骨骨折だけではBCIは滅多に発生しないと報告しています。
Dua A et al. Cardiol Res Pract. 2014;2014:629687 など
胸部外傷患者に対して胸部レントゲンとCTを行った大規模な後ろ向き研究では、292例の胸骨骨折患者(全体の2%)において、94%がCTのみで骨折が指摘され、7例がCardiac contusionと診断され、1例が胸骨骨折に対して外科的介入を必要としました。
Perez MR et al. Injury. 2015;46(7):1324
他にも、235例の胸骨骨折に治療を行った患者を対象とした単施設後ろ向き研究では、胸骨骨折の深達度や偏位の程度とBCIに関係性は認めませんでした。
Heidelberg L et al. J Surg Res. 2019;235:322
小児患者の注意点
成人よりも小児の方がBCIを疑うのは難しいと言われています。理由としては、小児の胸壁は成人よりも柔らかく、エネルギーが胸腔内臓器まで波及しやすいからと考えられています。心臓振盪が小児の運動選手に多く見られるのもこれが理由かもしれません。
ゆえに、小児におけるBCIは、外見では強い外力が加わったような所見がない場合があり、見逃す危険性があります。ですので、胸部打撲痕などの所見や圧痛、心雑音や脈に異常を認めた場合はBCIの可能性を考えましょう。
診断的検査
心電図
●胸痛や圧痛がある場合
●心疾患を疑わせるような既往歴がある場合(事故の前に失神や呼吸苦などがあった場合)
●BCIを疑うような所見や症状がある場合
に心電図を評価します。
BCIに伴う心電図所見としては、遷延する洞性頻脈、その他の不整脈、新規の脚ブロック、ST低下・上昇があります。しかし、受傷前に心臓イベント(ACSなど)をたまたま発症したからなのか、BCIによる直接的な影響なのか、身体的ストレスや重度の外傷のよる間接的な影響なのかを鑑別するのは困難です。
ある大規模な後ろ向き研究では、BCIと診断された患者群は、非BCIの胸部外傷患者群よりも2~4倍不整脈のリスクが高かったと報告していますが、洞性頻脈以外の不整脈が<1%であることや、洞性頻脈以外で最も多い不整脈がAFであること、さらにST変化や脚ブロックといった心電図異常については議論されていないことなど、この研究にはいくつかのLimitationがあります。
Ismailov RM et al. J Trauma. 2007;62(5):1186
心エコー
まずFocused Assessment with Sonography for Trauma (FAST)で心嚢液の有無などを迅速に評価します。さらに詳細に心エコー評価を行うことで、介入が必要な壁運動異常、中隔損傷、弁損傷などの有無の確認や輸液・強心薬の必要性の推定なども行うことができます。
ショックが遷延している場合には、経食道エコー(TEE)も検討します。やや侵襲的ですが、壁運動異常や弁、中隔の損傷がよりclearに描出でき、介入が必要な病変かどうかの判断に有用です。
重度な胸部外傷においてTEEと経胸壁エコー (TTE)をいずれも施行した前向き研究がありますが、TEEではおよそ98%の患者で最適な描出ができましたが、TTEでは60%の患者にしかできませんでした。さらに、心房・心室壁損傷や弁損傷のような重篤な損傷においてはTTEでは観察できなかったと報告しています。
Chirillo F et al. Heart. 1996;75(3):301
Cardiac biomarker
BCIにおけるCardiac biomarkerの有用性はまだ明確ではありません。
「Cardiac biomarkerは有用」説
・187例の鈍的胸部外傷患者を対象としたある前向き研究において、入院時もしくは病着後≦6時間のtroponin上昇は、不整脈やEF低下のリスク上昇と関連していました。
Rajan GP et al. J Trauma. 2004;57(4):80
・他の前向き研究でも、16例のサブグループにおいて初回の心電図で異常を認めても4~6時間でtroponinが上昇しなければ、有害事象は起こらなかったと報告しています。
Collins JN et al. Am Surg. 2001;67(9):821
・10編の前向き研究をまとめた鈍的胸部外傷入院患者1609例を対象としたreviewでは、高感度troponinが基準値下限以下であれば、臨床的に重篤な心合併症は起きにくい(陰性的中率が高い)という結果でした。
Guild CS et al. South Med J. 2014;107(1):52
「Cardiac biomarkerは有用でない」説
・複数の観察研究において、循環安定で、BCIを示唆する症状や所見がなく、心電図異常もない場合、CK-MBやtroponinの上昇は非特異的で、予後的な意味合いもほとんどないと報告しています。
Rajan GP et al. J Trauma. 2004;57(4):801 など
・非胸部外傷においてもtroponinが異常に上昇したという報告もあり、catecholamine-induced stressや、再灌流障害、oxidative injury、細菌やウイルス毒素、微小循環不全を伴うhypovolemic shockが関与している可能性があります。
Martin M et al. J Trauma. 2005;59(5):1086
まとめると、心電図異常がある患者においてはtroponin測定は予後予測にある程度有用かもしれないのですが、「troponinが陰性であれば、さらなる心合併症を起こさないから安心」といえるかどうかは不明です。また、循環が不安定な場合や他の重度な損傷がある場合、心電図で明らかな異常がない場合においてはcardiac biomakerを測定する意義に乏しいと言えます。
むしろ、Cardiac biomarkerで予後予測をするよりも、経過観察入院として、診察、心電図、モニタリングを繰り返し行い(特に最初の4~6時間)、スクリーニングした方がよいと思われます。
一方で、稀ではありますが、BCI患者において心電図で心筋梗塞を示唆するような所見を見つけた場合には、Cardiac biomarkerを測定し、循環器内科医または心臓血管外科医に相談するべきです。
画像検査
複数の観察研究で、CTやMRIによって心筋挫傷を同定できるかもしれないと報告されています。
Sade R et al. J Comput Assist Tomogr. 2017;41(3):354
BCIを示唆する所見としては、直接的なサイン(e.g. 心筋の減衰減少)や間接的なサイン(e.g. 肺水腫や虚血や弁損傷による心室拡大)などがあります。
Raptis DA et al. Radiol Clin North Am. 2019;57(1):201
また、心膜破裂症例においては、心嚢気腫や心膜の輪郭の不規則性や凹み、不連続性などを認めることもあります。
しかし、まだ治療方針を左右するほどの有用性があるかどうかを結論づけるにはデータが不足しており、まだ研究段階と言わざるを得ません。
損傷タイプごとの特徴とManagement
全身状態の安定化
BCIは胸部外傷に関連して発症するので、すべての患者において多臓器損傷が起こりえます。
JATECに沿って診療を進め、A、B、Cの安定化を図ります。
外傷による低血圧を認めた場合は、まず出血が原因と考えるべきであり、次に心タンポナーデや緊張性気胸を疑うべきです。最初からBCIを疑うべきではありません。
心破裂
特徴
心破裂によりblow outしている場合は、ほとんどの例で病院到着前に死亡しますが、稀に外科的介入で救命できることがあります。
また、心室損傷が重度ではない場合、数日遅れて心筋が壊死し破裂することがあります。
低血圧、頸静脈怒張、心音減弱(いわゆる、Beckの三徴)があれば、心タンポナーデを疑いますが、出血を伴う場合には所見が出ないことがあります。
治療
心タンポナーデと診断したら、心嚢穿刺を施行します。
心房損傷によって起こる心タンポナーデの場合は、外科的修復までは心嚢ドレナージでしのげる可能性があります。
手術室に移動できないほど循環が不安定な場合は、救急外来で開胸し、心タンポナーデを解除せざるをえませんが、蘇生が大変厳しくなります。
外科的修復は、sutureless techniqueなどによる破裂部の閉鎖となります。
心室中隔損傷
特徴
心室中隔損傷は稀です。
重症度は、取るに足らない裂傷から明らかな破裂まで様々で、弁損傷を伴う場合と伴わない場合があります。
心不全や大脈などを伴います。
治療
パッチ閉鎖などによる外科的修復を行います。
弁損傷
特徴
弁の単独損傷は稀です。
大動脈弁、三尖弁、僧帽弁の順に損傷が多いと言われています。
弁尖裂傷、乳頭筋断裂、腱索断裂などの報告があります。
症状は病変によりますが、新規の心雑音や右心不全、左心不全などをきたします。また、大動脈弁損傷の場合には、脈圧の増大が見られます。
損傷が軽度な場合には、初回には異常を指摘できず、後になって弁逆流が増悪、心不全化することもあります。
治療
弁置換や弁形成による外科的修復を行います。
心筋梗塞
特徴
稀ですが、報告はあります。
原因としては、冠動脈解離、冠動脈裂傷、血栓化などが挙げられます。
左冠動脈病変が最も多いと言われています。
治療
PCIまたは、CABGを行います。
Cardiac dysfunction
「Cardiac contusion (心挫傷)」や「Myocardial contusion (心筋挫傷)」という用語は定義が曖昧であるため、「Cardiac dysfunction」という用語が推奨されています。
収縮能低下などのCardiac dysfunctionがBCI患者においてどれくらいの頻度で発生するかは正確には分かっていません。そもそも多発外傷患者は、低血圧になる原因が他にもたくさんあるので原因特定も難しいと言われています。
動物実験では、BCIに伴って心収縮能が低下したり、酸素消費や乳酸産生が低下したり、右心系の圧が上昇したりと、不整脈以外にも複数の血行力学的障害を呈しました。なんらかの理由で、心筋代謝が障害された可能性がありますが、これらの変化は1日以内に改善しました。
Liu B et al. J Trauma. 1996;40(3 Suppl):S68
Liedtke AJ et al. J Trauma. 1980;20(9):777
不整脈
特徴
外傷患者においては頻脈の原因としてまず出血の有無が確認されるべきです。
出血が否定された上で、説明不能な持続性の頻脈や新規の脚ブロック、ちょっとした不整脈(PVCなど)があれば、BCIを疑います。
上室性不整脈(AFなど)~VFに至るまで様々な不整脈が報告されていますが、治療が必要になるほどの不整脈は少ないと言われています。
BCIの診断基準も曖昧で、発生率の算出も困難ですが、ある報告では、BCIの内、0~5%程度に発症していました。ちなみにこのデータでの診断基準には、Cardiac biomakerの上昇や心電図異常、エコー所見異常なども含まれています。
治療
BCI関連不整脈においての特有の治療についての研究はありません。標準的なACLSプロトコルに準拠した治療を行います。
予後
予後不良因子としては、trauma severity score (Injury Severity ScoreやOrgan Injury Scaleなど)が高いこと、短時間で診断していること(著しい所見があったことを示唆しています)、心タンポナーデや心破裂を伴っていること、入院時のバイタルサインが測られていないこと、大動脈、肝臓、脾臓、腎臓の合併損傷があることが挙げられます。心電図異常やCardiac biomarker高値のみでBCIと診断されているのであれば、予後は良好で、ほとんどの場合、後遺症はありません。
まとめと推奨
●BCIは様々な所見を示し、明確な診断基準もないため、損傷をより具体的に表現することが重要。
●重度の不整脈に対してはACLSプロトコールに沿って対応し、重度の損傷においては速やかに心臓外科医にコンサルテーションしましょう。
●不整脈、拡張期雑音、心不全所見などBCIが疑わしい所見を認めた場合は、心エコーを行い、循環器内科・心臓外科にコンサルテーションしましょう。
●循環が安定しているがBCIの懸念がある患者においては、経過観察入院とし、特に初回4~6時間は、診察、心電図などをこまめに評価しましょう。
●ルーチンにcardiac biomarkerを測定する必要はありません。(>60歳はその限りではありません。)
●小児の胸壁は成人より柔らかく、鈍的胸部外傷においてより胸腔内臓器までエネルギーが伝わりやすいことを念頭に入れましょう。

BCIは、現時点では分かっていないことが多く、信憑性の高い予後予測のツールもないため、「ちょっとでも疑ったら経過観察入院」が無難という結論になりました。
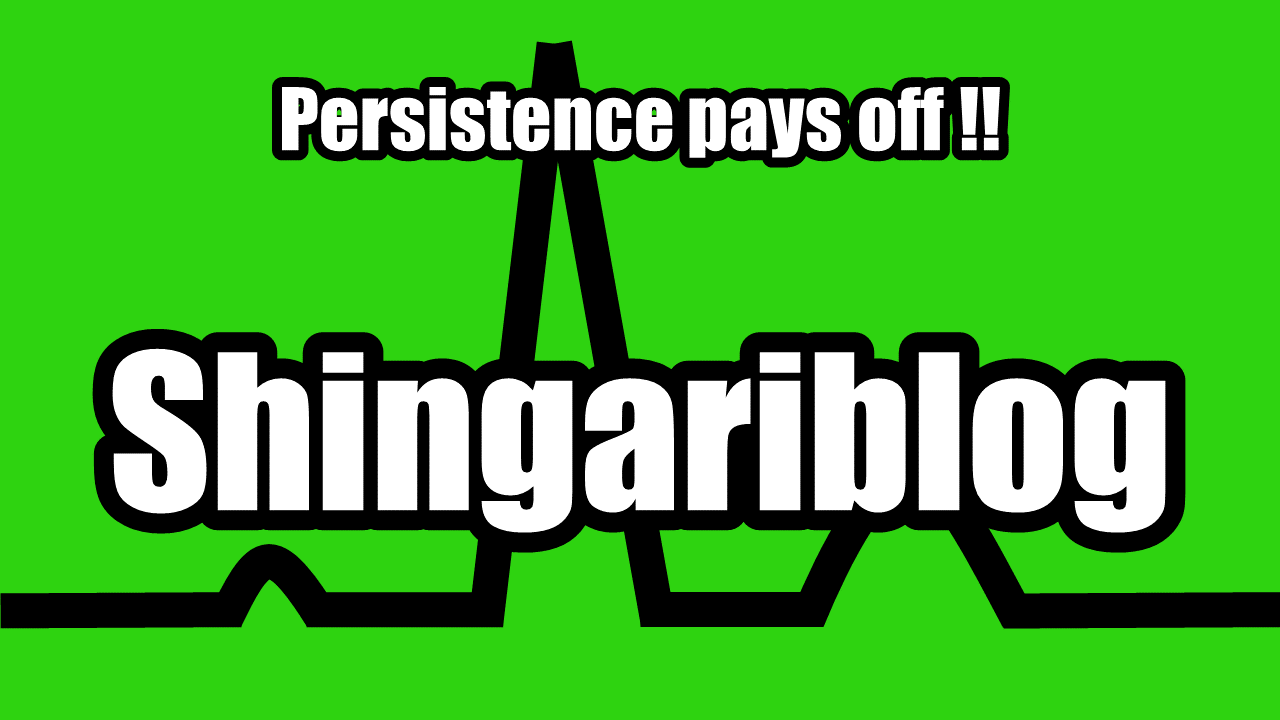

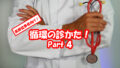

コメント