人工呼吸器装着患者を診る上で、いくつか知っておくべき呼吸の仕組み(呼吸生理)があります。
これを知っておけば、皆さんが担当する患者さんの呼吸の見え方がまた一段と変わるのではないでしょうか?
重要ポイント① 肺内シャントが多いとFiO₂が高くても意味がない
これに関しては、「医療従事者向け! 酸素投与について」や「医療従事者向け! 呼吸の診かた」でも少し説明させていただきました。
重複してしまいますが、非常に大事なポイントなので、再度、ご説明いたします。
肺胞が潰れると、そこで酸素の取り込みができなくなり、血液は肺動脈側から肺静脈側へただ通過するだけとなります。このことを肺内シャントといいます。
この肺内シャントの割合が多いほどFiO2に対するPaO2の変化が小さくなります。
すなわち、FiO2を上げてもPaO2が上がらない(血液内に酸素が取り込まれない)ことになるのです。
P/F<200になると、肺内シャント>20%という報告もあり、中等度以上に酸素化が不良であるときにFiO2を上げることのみで対応していくのには、限界があるということが分かると思います。
ですので、中等度以上の呼吸不全患者においては肺内シャントを減らす対策をとるべきだと言えます。
重要ポイント② ラプラスの法則
ラプラスの法則(Laplace’s law)という法則をご存じでしょうか?
この法則は、
表面張力Tに対して、半径Rと内圧Pの両方に比例する。 T∝R・P
といったものです。正直、ちょっとよく分かりませんよね?
一つ実験をしてみましょう。
Y字のチューブと、同じ素材で同じ大きさの風船を2つ用意する。 片方の風船(風船A)は膨らました状態で、もう片方(風船B)は潰れた状態でそれぞれチューブにつなぎ、チューブ内に空気を吹き込んだ。 風船はどうなるか?
この実験の結果を予想していただくと、意外と多くの人が「Bが膨らみ、AとBが同じくらいの膨らみ具合になる」と答えます。
しかし、答えは、「Aがより膨らみ、Bは潰れたままになる」です。不思議ですよね。

法則に当てはめると、AとBは同じ風船ですから、表面張力Tは同じです。
Aの風船の方が膨らんでいますから、Bの風船よりもAの風船の方が半径Rが大きいことになります。
つまり、内圧Pは、Aの風船の方が小さいということになります。
内圧P=風船を膨らますために必要な圧力ですから、Aの風船の方が「低い圧」で風船を膨らませることができるということになります。
いまいちピンとこない方は、「風船を膨らますときに、膨らまし始めと膨らまし途中とどっちが吹き込むのが大変か?」を想像してみると感覚的に分かりやすいと思います。
「膨らまし始めが大変」ですよね?
そうなのです。「潰れた風船は膨らますのが大変」なのです。
これが、人工呼吸器装着患者の肺においても同様のことが言えます。
すなわち、一旦、肺胞が潰れてしまうと、その後、空気を送っても、その肺胞は膨らまず、すでに膨らんでいる肺胞がより膨らんでしまう状態になってしまうのです。
重要ポイント③ 陰圧呼吸と陽圧呼吸の違い
陰圧呼吸
人間が普段、横隔膜を収縮させて、胸腔内を陰圧にすることで体外の空気を肺の中に引き込んで息を吸っています。これを「陰圧呼吸」といいます。
胸腔内に均等な陰圧がかかるため、肺も均等に膨らみます。どんな体勢でも肺が均等に膨らみやすいというのが特徴であるため、自発呼吸を温存すべきだという意見の理論的根拠の一つとなっています。
陽圧呼吸
一方で、人工呼吸器装着患者は、人工呼吸器より空気を送り込んで息を吸わせており、このことを「陽圧換気」と言います。
この場合は、膨らみやすい肺胞から膨らんでいき、潰れている肺胞は潰れたままになりやすい状況となります。
Pendelluft現象
近年、“自発呼吸関連肺障害”という概念が発見され、重度の肺障害をきたした患者において自発呼吸を温存すると、逆に肺障害をきたすかもしれないと言われるようになってきました。
この原因となる現象のことを「Pendelluft現象」と言います。
この現象は、「患者さんが自発的に吸気をした場合、胸腔内には均一に陰圧がかかる」という今までの概念を覆した現象であり、「重度の肺障害を有する場合、強い吸気努力により胸腔内の陰圧が不均一になる」という現象のことを言います。
具体的には、背側肺に重度肺障害をもつ人工呼吸器装着患者の場合、まず人工呼吸器から腹側の膨らみやすい肺に空気が送られます。その後、強い吸気努力によって、背側肺周辺に強い陰圧がかかり、空気が腹側肺から背側肺へ肺内を移動することになります。
重要ポイント④ 上ほど空気が入りやすく、下ほど血液が多い
人工呼吸器装着患者を管理する際には、看護師さんが一生懸命、患者さんの体位変換を頻回に行います。もちろん褥瘡予防という目的もあるのですが、呼吸の面でも大きなメリットがあります。
肺内の血液の分布は重力によって変化します。すなわち、立位の場合には尾側ほど血液が多いですし、仰臥位の場合には背側ほど血液が多くなります。
また、立位の場合には、頭側の肺胞ほど膨らみやすく、仰臥位の場合には腹側の肺胞ほど膨らみやすくなります。これは、肺自体の荷重などを受けにくくなるからです。
これらのことから、30° Head-upした仰臥位の患者さんにおいては、背尾側の血液が多いため、この部分の肺胞での酸素交換効率を上げることで、より効果的な酸素化改善が望めるということが言えます。一方で、この体位では、背尾側の肺胞には荷重がかかるため、虚脱しやすいということも言えます。
ですので、体位変換をしきりに行うことは、肺胞への荷重を減らし、虚脱肺胞を減らし、酸素化効率を上げていくという目的があると考えられます。
まとめ
★肺内シャントが多いと、FiO2を上げても効果が薄い
★陽圧換気と陰圧換気は肺への空気の入り方が異なる
★重度肺障害患者において自発呼吸を温存するかどうかは、まだcontroversialである
★背側肺を虚脱させないための努力(体位変換など)が重要
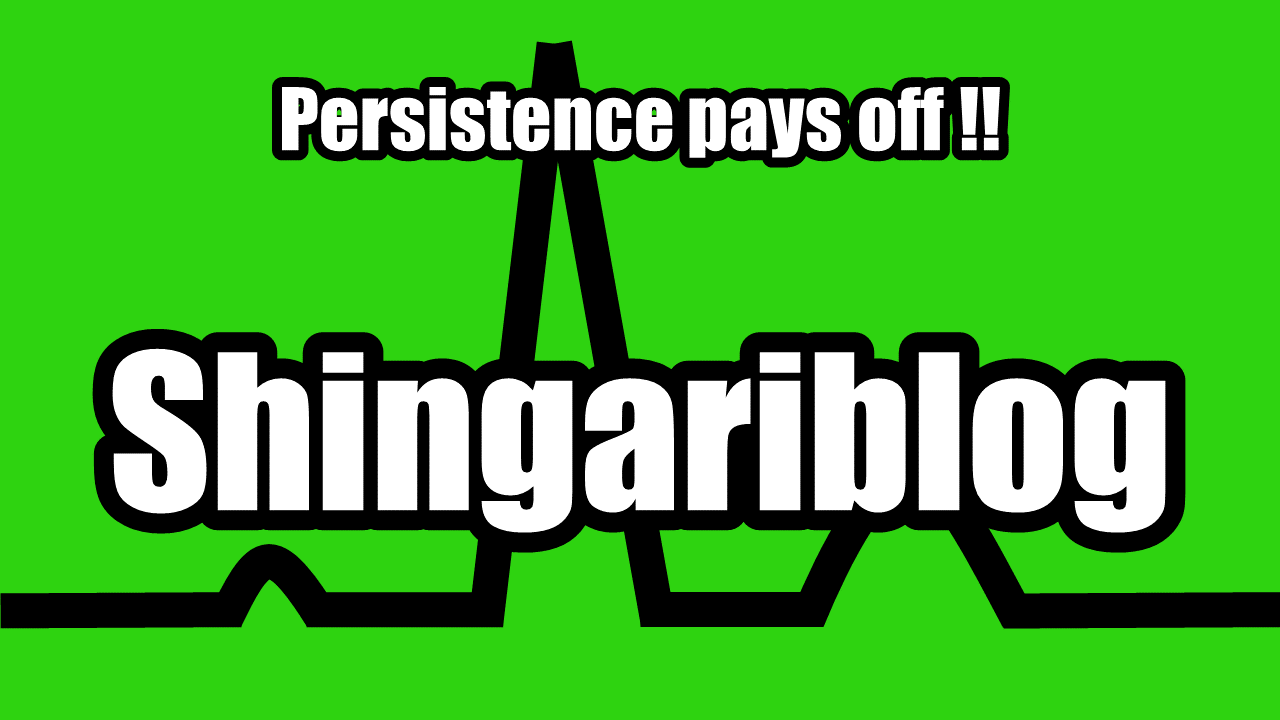
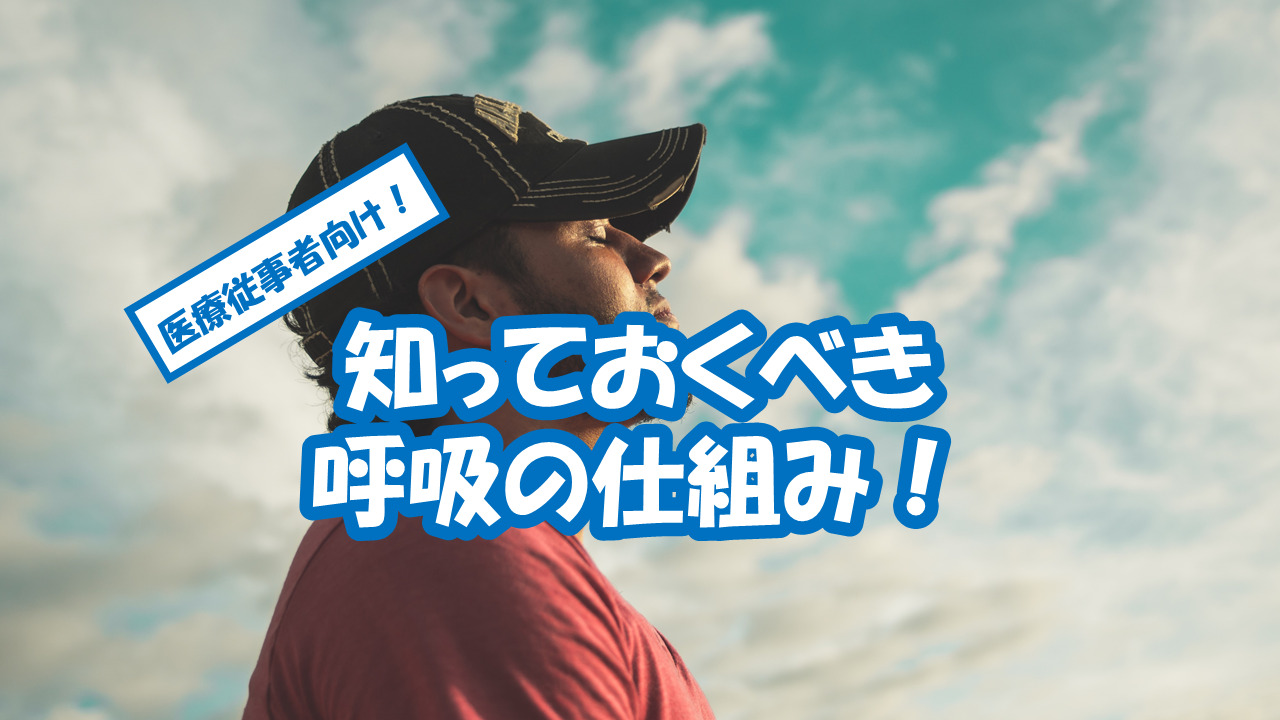

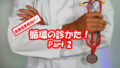
コメント