今回は、輸液管理について書かさせていただきます。
心臓血管外科に限らず、すべての患者さんに応用できる考え方だと思いますので、ぜひ読んでみてください。
輸液管理を行う場合、「なにを」、「どれだけ」投与するかという2つの事柄を決める必要があります。
なにを投与するか
「なにを投与するか」を考える上で、「どれだけ血管内に容量が残るのか」は必ず意識しなければなりません。そして、これを意識するために、まず人間の体液分布を知る必要があります。
体液分布を知る
人間の身体の60%は水でできています。そのうち40%は細胞内に分布しており、20%は細胞外に分布しています。そして、5%は血管内に分布しており、15%は血管外に分布しています。
輸液や輸血は、静脈内に投与しますので、それらはまず血管内に分布します。その後、製剤によって分布が変化していきます。
では、何が分布範囲の違いを生み出しているのでしょうか。
浸透圧が製剤の分布範囲に影響する
輸液、輸血製剤の分布範囲の違いは「浸透圧」が大きく影響しています。
そして、浸透圧には以下の2種類の浸透圧があります。
- 膠質浸透圧
- 晶質浸透圧
膠質浸透圧
膠質浸透圧というのは、アルブミンなどの分子量の比較的大きい物質により生み出される浸透圧です。
血管は内皮細胞によって内腔面がびっしりと覆われているのですが、その内皮細胞と内皮細胞の間にはわずかな隙間(内皮細胞間隙)があります。
分子量の小さな物質はこの隙間を自由に行き来できるのですが、分子量の大きな物質はこの隙間が通れません。ゆえに分子量の大きい物質を含む製剤(膠質浸透圧が高い製剤)は血管内に残りやすく、分子量の大きい物質を含まない製剤(膠質浸透圧が低い製剤)は血管外に出ていきやすいということになります。
晶質浸透圧
晶質浸透圧というのは、電解質(主にNa)により生み出される浸透圧です。細胞は細胞膜という膜により包まれていますが、細胞膜は半透膜になっており、自由水は容易に通れますが、Naなどの電解質は容易に通れないようになっています。
ゆえにNaを多く含む製剤(晶質浸透圧が高い製剤)は細胞外に残りやすく、Naをあまり含まない製剤(晶質浸透圧が低い製剤)は細胞内にまで分布しやすいということになります。

輸液・輸血製剤の違いを知る
血管内に分布する製剤
血管内に分布するためには、膠質浸透圧が高い製剤(分子量が大きな物質を含む製剤)である必要があります。
具体的には、アルブミン製剤(アルブミナー、25%アルブミンなど)、HES製剤(ヘスパンダー、ボルベンなど)、輸血(赤血球、新鮮凍結血漿、血小板)といったものになります。

これらの製剤はほぼ血管内に残ります。
つまり、1L投与したと仮定すると、投与直後は血管内容量が1L増えることになります。
細胞外(血管内・血管外)に分布する製剤
細胞外に分布するためには、分子量が小さく、Naを多く含む製剤(膠質浸透圧が低く、晶質浸透圧が高い製剤)である必要があります。具体的には、生理食塩水、細胞外液補充液(ソリューゲン、リナセートなど)といったものが挙げられます。

これらの製剤は細胞外に残ります。
つまり、1L投与したと仮定すると、投与直後は血管内容量が250ml (=1L×5/20)増えることになります。
細胞外+細胞内に分布する製剤
細胞外+細胞内と全身に分布するためには、分子量が小さく、Naをあまり含まない製剤(膠質浸透圧、晶質浸透圧ともに低い製剤)である必要があります。具体的には、5%糖液などが挙げられます。

これらの製剤は全体にまんべんなく分布します。
つまり、1L投与したと仮定すると、血管内容量は83ml(=1L×5/60)増えることになります。
1号液(開始液)、3号液(維持液)
血管内への分布の仕方という観点では、前述の3種類の製剤で考えていくのが分かりやすいのですが、日常診療においては、1号液(KN1号、ソルデム1号など)、3号液(KN3号、ソルデム3号など)がよく用いられます。
これらを用いる場合には、
- 1号液=細胞外液1/2+5%糖液1/2
- 3号液=細胞外液1/3+5%糖液2/3
といった感じに混ぜたような製剤と考えればよいでしょう。

1L投与したと仮定すると、血管内容量は
1号液は、167ml(=500ml×5/20+500ml×5/60)
3号液は、139ml(=333ml×5/20+666ml×5/60)
増えたことになります。

どれだけ投与するか
「どれだけ投与するか」を考える上で、私は以下の5つの項目を意識しています。
- ショックからの離脱
- 現在の血管内volume
- 時期
- IN/OUTバランス
- 肺を守るか、腎を守るか
ショックからの離脱
患者さんの輸液を開始する場面は様々なシチュエーションがあります。例えば、病棟で食事が摂取できなくなった場面、救急外来でショックとなっている場面、病院内で急変してしまった場面などです。
それらの場面の中で、Hypovolemic shockとなっている患者さんに輸液を開始する際には、どれだけ輸液を投与すればよいかを考えてみます。
ここで参考となるのが、ATLS classification of blood lossという血液喪失の分類です。
| 出血量 (喪失割合) | Class 1 (<15%) | Class 2 (15-30%) | Class 3 (30-40%) | Class 4 (≧40%) |
| HR(bpm) | <100 | ≧100 | ≧120 | ≧140 |
| sBP(mmHg) | 正常 | 正常 | 低下 | 低下 |
| RR(/min) | 14-20 | 20-30 | 30-40 | ≧35 |
| 精神症状 | 軽度不安感 | 中程度不安感 | 高度不安感 混乱 | 混乱 昏睡 |
シンプルなhypovolemic shockであると仮定すると、全血液量の15%を喪失するまではほぼ無症状、無所見で、15%を超えるとHRを上げたりするなどの心拍出量を上げるための代償反応が働き、30%を超えると代償反応では代償しきれず、血圧が下がり、40%を超えると臓器障害なども進んでくるようなイメージです。
ここで、患者さんがClass 3の状態である場合(体重50kgと仮定)の輸液量を考えてみます。
血液量は、体重の約8%に相当しますので、約4Lとなります。
Class 3の血液喪失(≧30%)がありますので、1.2L(=4×0.3)の血液喪失があると推定できます。
もともとのHctが40%としますと、喪失した血漿量は0.72L(=1.2×0.6)となります。
前述したように細胞外液の1/4が血管内に残りますので、喪失した血漿量を全て輸液で補おうとしますと、約2.8L(=0.72×4)の輸液量が必要であることが分かります。
ですので、Hypovolemic shockの場合には、速やかに急速輸液を行い、Class 3、Class 4からの離脱を図ります。
一方で、2.8L以上輸液負荷しても状態が改善しない場合は、さらなる血液喪失があるか、Hypovolemic shock以外のShockの病態が潜んでいる可能性を考慮すべきです。
ただし、近年は、輸液負荷による血液希釈による有害事象(凝固障害など)も指摘されておりますので、2.8Lという数字は絶対的なものではなく、あくまでも目安であることは留意してください。
現在の血管内volume
輸液量を決める際に検討すべき2つ目の項目は、患者さんの現在の血管内volumeです。
Hypovolemiaなのか、Hypervolemiaなのか、輸液反応性があるのか、ないのかを判断することで輸液流量を増やすべきか、減らすべきかを判断します。
このことに関しては、別稿をご覧ください。
時期
3つ目の項目は「時期」です。
手術や重症感染などの強いストレス侵襲が人体に加わった場合にどのような生体反応が生じるのかを知り、現在、その生体反応のどのプロセスに患者が位置しているのかを意識することは輸液戦略を考える上で非常に大切です。
通常、血管壁内腔は内皮細胞により密に覆われており、血管内に水を保持する役割を果たしています。この水を保持する役割にはグリコカリックスという内皮細胞表面の構造が寄与していると言われています。人体に強いストレス侵襲が加わると、グリコカリックスの構造が乱れ、血管内の水、タンパクが血管外に漏出するという現象が起きます。このことを血管透過性亢進といいます。
また、細胞外血管外の部分は細胞外マトリックスという支持組織が多くを占めておりますが、細胞外マトリックスは高い吸水性をもつヒアルロン酸をコラーゲン線維が取り囲むような構造をしています。
しかし、強いストレス侵襲が加わると、コラーゲン線維の構造が乱れ、ヒアルロン酸が剝き出しとなります。
ゆえに、ストレス侵襲が加わった直後は、血管透過性亢進によって血管外へ漏出した水が、剝き出しになったヒアルロン酸に吸水されるという状況が起こり、輸液負荷を行ったとしても、血管内にはvolumeが残りづらくなります。
血管透過性亢進によって、漏出したタンパクの中にヒアルロニダーゼなどのヒアルロン酸を分解する酵素も含まれています。ヒアルロン酸はこの酵素により数日間かけてゆっくり分解され、ヒアルロン酸に吸水された水は徐々に自由度が上がっていきます。
そして、その後、自由度が上がった水は、リンパ系を介して血管内へ戻っていきます。
ゆえに、ストレス侵襲が加わってから数日後には、輸液流量を減らしているのにも関わらず、血管内volumeが増えていくという状況が起こります。このことをRefillingといいます。

つまり、強いストレス侵襲が加わった患者の輸液は、
- ストレス侵襲直後は、臓器障害が進まない程度に可能な限り輸液量を制限すること
- Refillingによるhypervolemiaに注意すること
が大切であると言えます。
IN/OUTバランス
「どれだけ輸液をするか(=IN)」を決めるためには、「どれだけ血管からvolumeが出ていくか(=OUT)」を把握する必要があります。
OUTとしては、
- 尿量
- 便量
- NGチューブからの排液
- ドレーン排液
- 不感蒸泄・汗
- 血管透過性亢進による血管外漏出量
が挙げられます。
このうち、尿量、便量、NGチューブからの排液、ドレーン排液は測定可能ですが、不感蒸泄や汗、血管透過性亢進による血管外漏出量は測定が困難です。
ゆえに、測定可能な項目を参考にした上で、暫定的に輸液量を決めていき、循環のパラメータの推移を追いながら調整していくということになります。
また、体重の推移をみていけば、IN-OUTをある程度、定量化することもできます。
肺を守るか、腎を守るか
最後に、輸液の投与量で悩んだら肺を守るか、腎を守るかを考えるようにしています。
輸液を極力絞ると腎血流が減り、腎前性腎不全のリスクが上がりますが、肺うっ血は改善します。一方で、輸液を負荷すると腎血流が増え、腎前性腎不全のリスクが下がりますが、肺うっ血は増悪します。
このように、輸液管理を行う際には、肺と腎への影響を常に観察する必要があります。
例えば、慢性心不全が高度に進行した場合、前負荷の変化に見合った心特性の調整ができず、至適なvolumeの範囲が極めて狭くなります。すなわち、輸液を絞れば低心拍出症候群(LOS)となり、輸液を負荷すれば肺うっ血により呼吸が悪化するという事態に陥ります。
それでも至適なvolumeを維持し続けるしかないわけなのですが、至適なvolume自体が存在しないレベルまで慢性心不全が進行した場合には、その患者さんの肺や腎の余力がどこまであるのかや、どこまでの治療を望まれるのか(人工呼吸器管理や透析など)といったことを考慮して輸液流量を決めていくことになります。
まとめ
★輸液・輸血製剤によってどれだけ血管内にvolumeが残るのかを意識する
★輸液流量は、ショックからの離脱、現在の血管内volume、時期、IN/OUTバランス、肺or腎という5つの項目を総合的に判断して決めていく
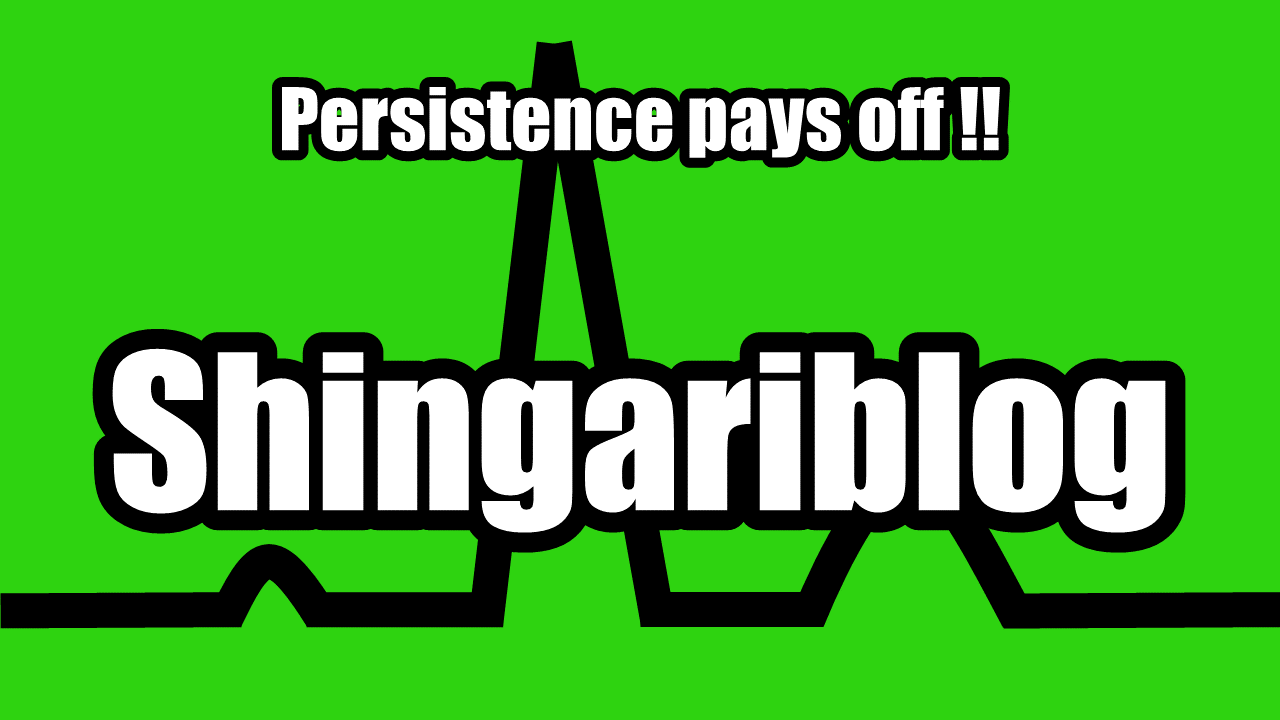




コメント